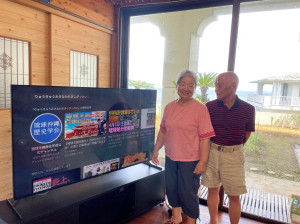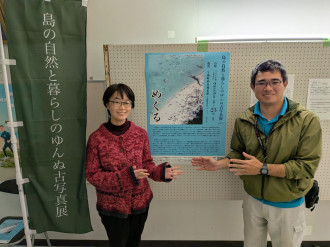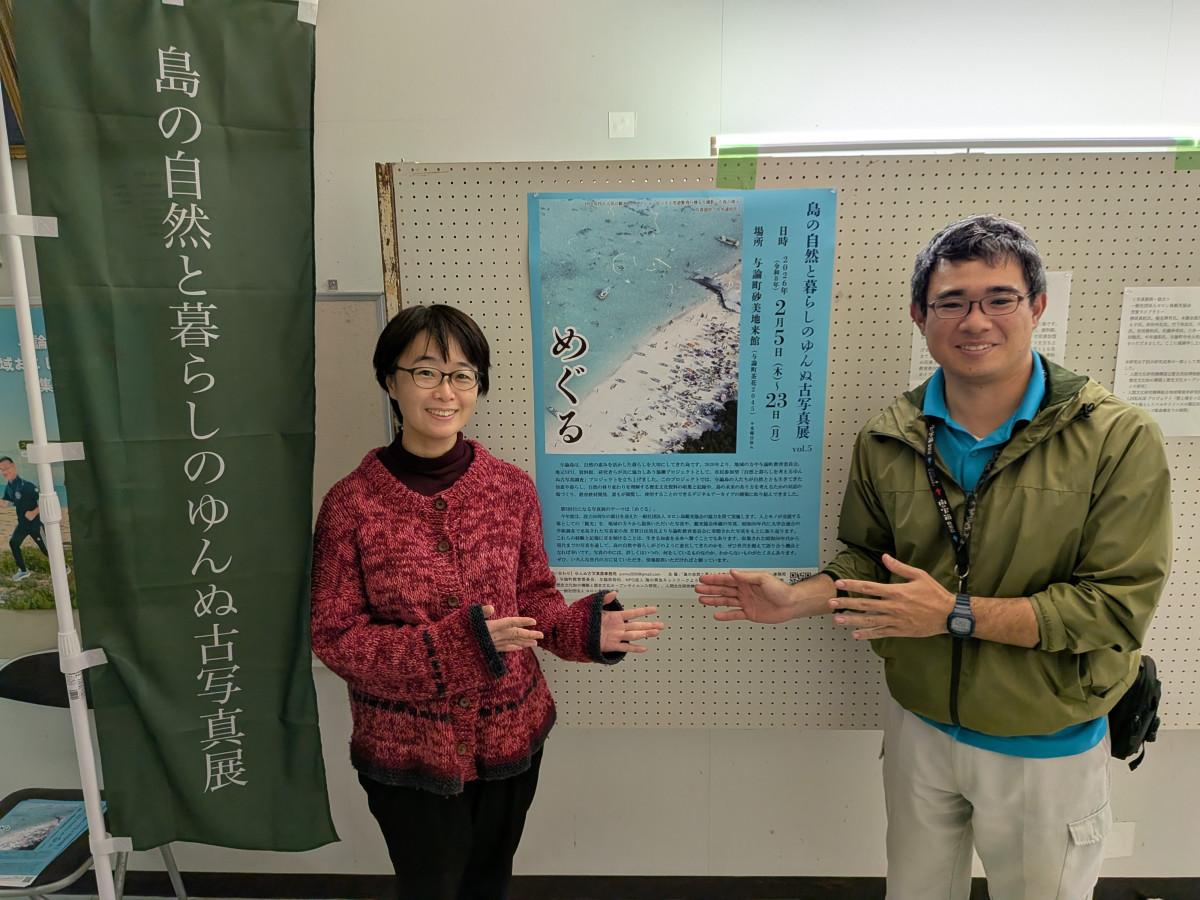沖永良部島の和泊町が「中学校あり方座談会」 島の学校の未来を話し合う

沖永良部島の和泊町内の中学校の統廃合などのあり方について行政職員と地域住民が話し合う「和泊町立中学校あり方座談会」が11月10日、大城小学校(和泊町大城)の音楽ホールで開催された。
少子化に伴う生徒数の減少や校舎の老朽化などの課題を念頭に、児童が将来安心して学べる場を確保するため、町民の意見を募る目的で開いている。この日は6回目で、これまでに各校の学校運営協議会や小中学校に通う生徒の保護者、校区住民を対象に行い、延べ100人近くが参加。活発な議論が交わされてきた。
同町の人口は2014(平成26)年の6898人から2024年には5987人に減っており、町内の中学生の総数は2021年度から本年度までに192人から167人へと減っている。校舎の改修や修繕費用は2034年度までに約22億円が必要と試算しており、このうち町の負担額は約15億円に上る。
同町教育委員会はこうした現状を踏まえ、小規模校の「きめ細かい教育が行え、リーダーシップが育ちやすい」「競争心や向上心が育ちにくい」などのメリットとデメリットや、他地域の事例を共有した上で、統合、維持、義務教育学校の設立などの選択肢を提示しながら会を進行した。
座談会では「学校は地域のシンボルなので統合したくない」「統合を考えていかないと教育環境が維持できない」「知名町や他の校区住民とも話し合った方がいい」など活発な意見が交わされた。通学先が遠いと部活動の時間を確保することが難しくなったり、保護者の送迎が必要になったりすることなどを念頭に、スクールバスなどの送迎環境の整備や小規模校のデメリットの解消という具体的な議論にも話は及んだ。
和泊町教育委員会の安田拓さんは「AIやICTなどの技術が進んでも、人と人との触れ合いの間で生まれる体験やコミュニケーション能力は将来、最も大事な部分。学校に行きづらい子どものケアについても、どのようにサポートできるかを考えていきたい。座談会を通して、まずはみんなで教育環境を考える素地ができて良かった」と今後の展開に期待を込める。
本年度中は他市町村の情報収集と地域住民や保護者の意見集約を行い、2026年度に学校のあり方検討会を開催予定。