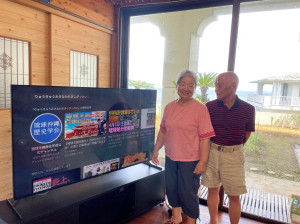徳之島・山小学校児童、「命をいただく」を学ぶ 自前食材で鶏飯作りに挑戦

徳之島町の山(さん)小学校(徳之島町山)の生徒たちが10月18日・19日の2日間、家庭教育学級の時間を使い鶏飯作りに挑戦した。
地元の食材を用い、地産地消をテーマに行った今回の鶏飯作り。使った米は自分たちで田植えに始まり、収穫、脱穀、精米したもの。18日は6羽の鶏を用い、地域の人と一緒に実際に鶏を絶命させ、血抜きを行い、羽根をはぎ取り、部位を丁寧に分けていく作業を行った。当初は子どもたちに戸惑いもあったが、作業が進むにつれ積極的に参加する子ども、鶏の体のつくりに興味を示す子どもも多く見られた。普段食卓に並ぶ食材は「多くの生命をいただいている」ことを子どもたちも感じ取っていた。その後、スープのだしとして利用する部分、ササミとして使う食材などに細かく分けていった。
翌日には、島の鶏卵から作った卵焼きを細かく切り、シークニン、ニンニク、ゆずこしょうなどで味付けたパパイア漬けを刻み、自分たちで育てたシイタケを味付けし、鶏ガラを煮込みスープを準備。包丁片手に真剣に卵焼きに向き合う様子や胸肉を細かく裂いていく作業を保護者らが見守った。約2時間で全ての具材がそろい、ドラゴンフルーツ、島バナナで作った特製ジュースも食卓に彩りを添えた。
食事会には、田植えなどで世話になった手々(テテ)集落の小倉区長と政さんを招待。2人は手々集落で歌われている田植え歌を披露。この歌がもともと山集落から伝わってきたことも紹介し、失われつつある稲作文化の継承について語った。
自分たちで準備し、調理した鶏飯をお代わりする子どもも多く、食事会は子どもたちの笑顔であふれた。6年の玉城湖華さんは「みんなで料理したので、普段食べている鶏飯よりおいしかった。私たちは多くの命をいただいていることを実感した」と初めての経験の感想を話した。